「KOBEくらしのレポート」は、市内の各地域にいる「くらしのパートナー※」から寄せられた悪質商法や消費者トラブルについての情報を、読んでいただきたやすいようレポートにまとめたものです。(※くらしのパートナー)
家族や友人の方への注意の呼びかけなどに、ぜひ活用してください。
2025年3月号 目次
印刷用PDFデータ
KOBEくらしのレポート2025年3月号(カラー版)(PDF)
KOBEくらしのレポート2025年3月号(モノクロ版)(PDF)
代引き配達を利用した通販に注意
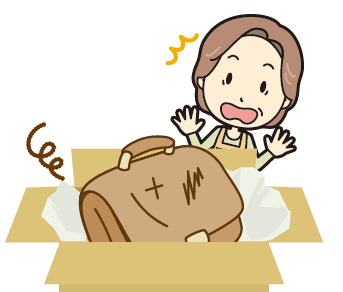
事例
『ブランド品を安く購入できる』というSNS広告を見てジャケットを購入し、代引き配達で受け取ったが、届いたものは誰が見ても偽物とわかるものだった。
「代引き配達」とは
インターネット通販などで購入した商品を受け取る際、配送業者に商品の代金と送料、手数料を合わせた金額を支払い、商品を受け取るサービスです。代金を支払った後でないと商品の中身を確認することができないため、トラブルになることがあります。
注意点
代引き配達を利用して代金を支払った場合、原則として配送業者から料金は返金されません。そのため商品が壊れていた等の問題がある場合は、配送業者ではなく販売店(サイト)に連絡しましょう。
偽通販サイトに注意
事例の他にも「注文した商品が届かない」「クレジットカード情報等の個人情報を搾取された」という報告もあります。少しでも怪しいと感じたら取引するのは避けましょう。
偽通販サイトの特徴
- 販売価格が大幅に値下げされている。
- 他のサイトにない商品を定価よりも安価な値段で取り扱っている。
- サイトの日本語の表現や字体がおかしい。
- 代引き配達のみ等、支払方法が限定されている。
- 販売事業者の住所や連絡先の記載がない、または虚偽の情報である。
屋根工事のトラブルに注意!

国民生活センターが集計した全国の相談傾向を見ると、年齢が上がるほど多くなる相談の一つに、「屋根工事」のトラブルがあります。
事例と一緒に注意点を確認!
リフォーム工事をしているという人物が、「無料で点検します」と突然家に訪問してきた。そろそろ外壁や屋根の塗り替えが必要だと考えていたため、すぐに点検をお願いした。
- 突然訪問してきた業者に、安易に点検をさせない!
- 『 無料』という甘い言葉を掛けられても、怪しいと感じたらきっぱりと断る!
点検後、男がとった写真を見せながら「スレートを止めている釘が何本も落ちている状態です。このままだと雨漏りや近所に迷惑がかかるかもしれません。修理をするならお電話ください」と言って名刺を置いて帰った。
- 点検する場所をわざと壊してから撮影したり、別の場所で撮った写真を見せたりする悪質な事例もあります!
見積を依頼すると、役員の人と先日の訪問者が来て合計金額が240 万円と記載された見積書を見せられた。断ろうとすると役員が「今契約していただけるなら140 万円にします」と言ってきた。
- 初めに高い金額を提示してから値引きをすることで、安いと感じさせ契約を迫ります!
- 修理等が必要な場合は、自分で複数社の見積を取ってから検討する!
困ったら早めに相談!
工事後でもクーリング・オフできる可能性があります。困った時は、契約書やメモなど資料を手元に揃えて、消費生活センターにご相談ください。
リフォームや修繕の進め方などでお困りの場合はすまいるネットにご相談ください。
電 話:078-647-9900
受付時間:10:00~17:00(水曜・日曜・祝日定休)
修繕やリフォームについてはこちら(すまいるネット)
次々と高額商品の購入を迫られる

事例
認知症の疑いがある家族が友人に誘われて、事業者の車で着物や装飾品等の展示会、また食事会等に連れて行かれている。会場に行くたびに勧誘され、言われるがまま商品を購入しているようだ。年金の約8割をその支払いに充てており、生活に困っている。
展示会商法とは
展示会や豪華な食事会・旅行会等に誘い、次々と高価な着物や絵画、アクセサリー等を購入させる商法を「展示会商法」と呼びます。
「無料でご覧になれます」「入場者プレゼントがあります」「特売会をしています」などと甘い言葉をかけられ、一度その場に行ってしまうと「高いからいらない」「必要ない」と言っても執拗に契約を迫られ、会場から出にくい状況に追い込まれる可能性があります。
高齢者が被害に遭ってしまうと生活が困窮する等、日常へ大きな影響を与えるため注意
が必要です。
アドバイス
- まず、誘われてもそのような場に行かないことが最も重要です。
- 強引に購入を迫られても、必要がなければきっぱりと断りましょう。
- 本人は喜んで通っている場合もあるため、家族や周りの人の見守りが大切です。
- 展示販売ではクーリング・オフができない場合もありますが、複数人に囲まれて仕方なく契約した場合等は、クーリング・オフできると考えられます。
- 困った時は早めに消費生活センターに相談しましょう。
キャッシュカードの暗証番号は教えない!

事例
- 金融関係者と名乗る人が自宅を訪問してきて、「通帳とキャッシュカードがリニューアルする」と説明を受けたため、その男性に通帳とキャッシュカードを渡してしまった。
- 警察官を装った人物から「あなたの口座が不正利用されています。お金を取り戻す手続きをする為にキャッシュカードが必要なので今からそちらへ伺います」という電話があった。訪問してきた男性に暗証番号を書いたメモとカードを渡すと、それらを封筒に入れ、「手続きが済むまで開けずに保管しておいてください」と指示された。後日、確認すると偽物のカードとすり替えられていることに気が付いた。
被害者の声
- 自分は絶対に騙されないと思っていた。
- 詐欺犯から電話や訪問があるとは思わなかった。
- 口調が丁寧で、身なりもしっかりとしており、詐欺を働くような人には見えなかった。
詐欺から身を守るために
「自分は大丈夫」と楽観視するのではなく、「次は自分かもしれない」という危機感を持って行動しましょう。また、家族が被害に遭わないためにも、電話をかける等して安否確認をするとともに、詐欺の事例や注意する点等について家族に伝えるようにしてください。
相談窓口のご案内
上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。
原稿作成:消費生活マスター
情報提供:くらしのパートナー、あんしんすこやかセンター
